*筆者は、非英語圏フィンランドにて1年留学しました。英語圏とはまた違った状況です。また、これは筆者が ”空気を読んでみた” 記録です。
「You know」
ネイティブの口癖!として有名ですね。
「You know」を、日本語では「えっと」「ほら」「わかるだろ」という意味で
ネイティブはよく使ってるよ!って。
それはそうなんですが、頻繁に使いすぎている人はあまり印象が良くないです。
特に相手から意見を求められた場面で、
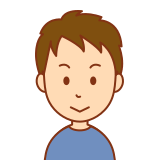
「だってさ、あー、you know?」
と癖で使ってしまう人を見かけますが、そういう時、
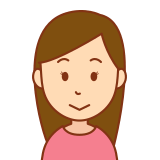
「No (いや、わかんねーよ)」
と返されます。
こういうように、中身が伴っていないのに You know を乱用すると、
流暢さやネイティブっぽさのアピール(?)のつもりの you know が、逆効果です。
「あのさ」という感じで、文頭に付け足す、または、
きちんと自分の意見をはっきり述べた上で、
最後に、You know? をたまに付け足して使う、程度の使用がちょうどいいと思います。
そのうちYou know 無しでは話せなくなってしまいます…!!
なるべくYou knowを使わない生活に慣れておいた方が賢明です。
Oh My God!
これは有名な話ですね。
ヨーロッパにはたくさんのクリスチャンがいます。
クリスチャンたちは、決して軽々しく「God」の単語を使いません。
軽々しく神様の名前を口にすることは、神への冒涜であると考えられているためです。
同じような表現の
「Jesus Christ!」 「Oh Lord!」
なども同様です。
その人たちがいるかもしれない人混みのど真ん中で
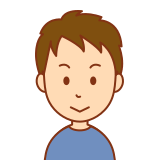
Oh My God!
と叫ぶ勇気はありますか??
たぶん何も言われないと思いますが、心の中ではきっと『アッ…』って思ってます。
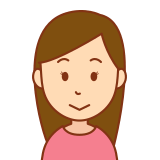
『きっと映画とかから習得した英語表現をいきって使ってるんだわ…』
と、まだ英語駆け出しの子、とも思われそうです。
やめときましょう…
Shit! / Fuck! / Damn (it)!
こちらも、ネイティブのちょっと悪い口癖として有名です。
筆者は留学中、耳にタコができるほど聞きました。
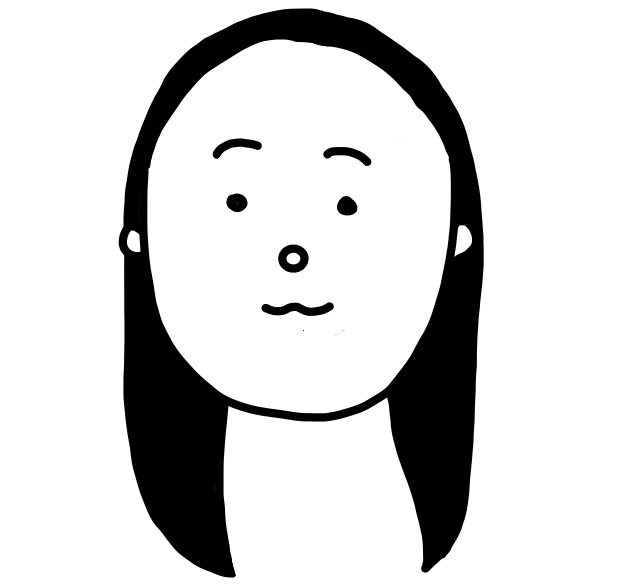
よく飽きもせずに…。そこまでしてそれを繰り返したいのかー!?
と叫びたいです。
ヨーロッパの学生たち、男女共みんな、使ってます。
一見、品のよさそうで賢そうなイケメンも美女も、
みんな事あるごとに
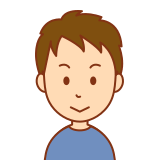
Sh**********t!!
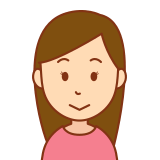
F******ck!!!
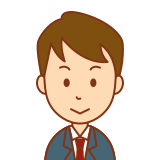
damn it!!!!!
と叫び合っています。
みんな使ってるならいいじゃない、と思うかもしれませんが、
結構な頻度で使用しているヨーロッパの学生を見てると、
おそらく彼らも、興味本位で繰り返し使っているうちに
口癖になってしまい、それ以外の表現が浮かんでこない中毒状態に陥っています。
たまにならまだいいんです。
でも、頻繁に使う人は印象があまりよくありません。
あ、優しくて賢い素敵な人だな、と思っても、後で
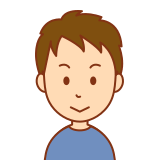
Sh*t!!
を連呼しているようだと、「あれ、思ってた人と違うかも…」
と思ってしまいます。
ネイティブの常套句、として知られていても、
罵り言葉を使わないように気を付けている人もたくさんいます。
使わないように気を付けることは、変でもなんでもありません。
それに、「ネイティブが日常的に使ってるから」汚い言葉を使っても大丈夫、ってほんとにそうでしょうか?
普段何気なく用いる言葉が、自分の印象だけでなく、自分の周りに集まる友だちを決め、
長期的には、自分の人格形成にも影響するのです。
「友達が頻繁に使ってて、自分も友達みたいにカジュアルに話して仲良くなりたい」
かもしれません。
でも、考えてみてください。
人に映る自分の第一印象は、”罵り言葉を頻繁に使っている人” がいいでしょうか。
また、本当に自分に合っている友達は、
言葉・国籍・年齢 何もかも関係なく、自然に集まってくるものです。
ちょっと使う言葉にもう少し注意を払ってみましょう。
少なくとも、罵り言葉がマイノリティの世界の方が、そうでない世界より素敵です。
アメリカ人ラリーに教わった、”罵り言葉を使わない罵り方” はこちらから。

フィンランド語の罵り言葉(Perkele! Vittu!等)だって、相当印象悪いです!!
話題作りに持ってこいなのかもしれないけど、あまり居心地の良い話題でないことは確か。
(筆者は一度言ってみたところ、「お願いだから使わないで!」と友達に懇願されました)
「Where are you from?」
これは全然使ってもらって構わない表現です。
留学生たちにとっては、相手を知り合う上で必須の質問ですね。
なんでここに候補として挙げたか、というと、
この質問を不快に思う人も、たまにいるからです。
留学先では様々なバックグラウンドを持った人たちと出会う機会が日常的に存在します。
その中には、「出身地どこ?」と気軽に聞いて、一言で返せない人たちもたくさんいます。
彼らの出身地は一つとは限らない。
彼らがアイデンティティを感じる出身地は一つとは限らないのです。
<私の失敗談>
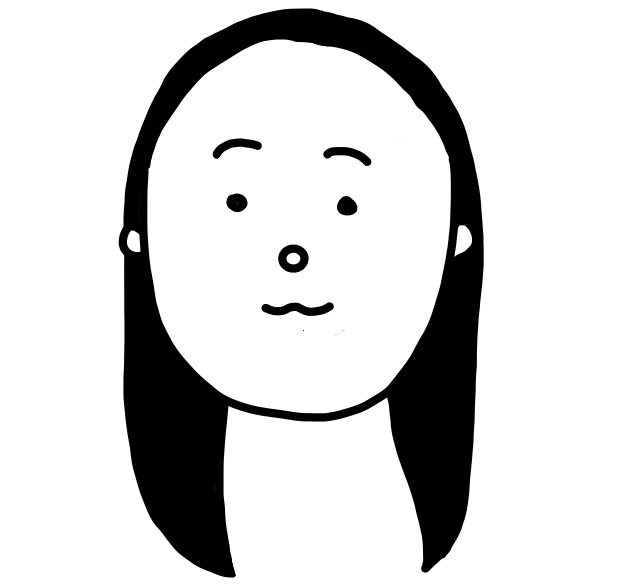
「出身はどこ?」
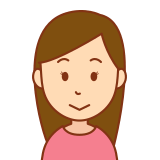
「…あー、それはたぶん聞きたくないと思うよ。
私は世界のいろんな国に住んでたから、自分のアイデンティティがどこの国なのかは一言で説明できなくて…」
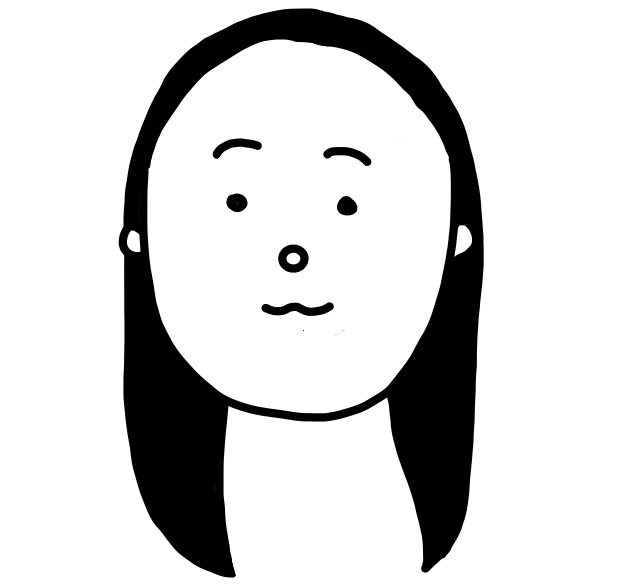
「そうなんだ!とっても興味深いね!時間かかってもいいから、聞いてみたいな!どんな所に住んでたの?」
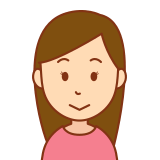
「えっと…あのー、いやほんとにいろんな国に行ってたから…」
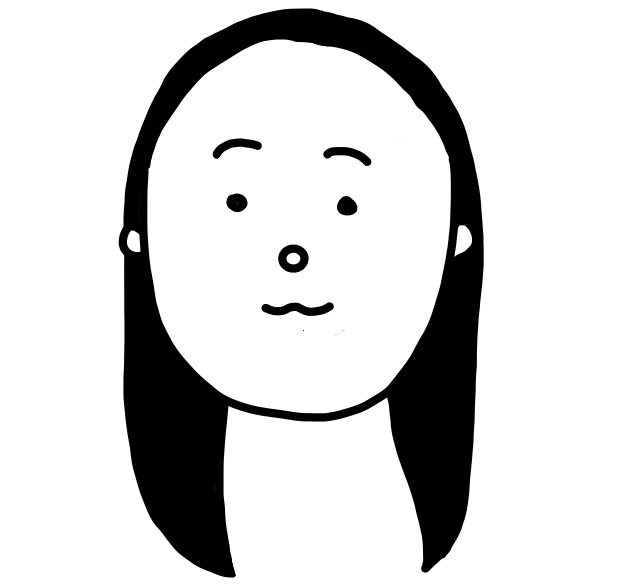
「えっと、じゃあ…最初の国はどこだったの?」
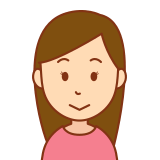
「あーーーもう!私は答えたくないの!(怒)」
ということがありました。
当たり障りのない質問 “出身はどこ?”
こんな「ザ・無難」な質問も、世界では無難じゃなくなる危険性があるのです。
世界に出れば、日本の当たり前は当たり前じゃなくなる。
もしかしたら、日本国内でも、当たり前と見なされるべき質問じゃないかもしれません。
そのことを改めて学ぶことができる一例だと思います。
その他、外国ですると誤解を生む動作や、言葉をこちらで解説しています。
フィンランドの文化:「嫌なことには嫌と言え!」

こちらの記事で私がチューターに「お迎えはいらないから」と言った場面。
フィンランド人の友人に言わせれば、
これはまさしく “日本人の謙虚さ” と “フィンランド人の率直さ” の文化摩擦の典型例だそうです。
フィンランドの人は、思っていることを比較的率直に言う文化の中で育ってきています。

ねえ、今日スケートに行かない?
でも私は今日、カフェでケーキざんまいするつもりだったのになぁ…
こんなときあなたならどう言いますか?
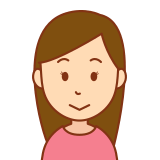
あー…行けたら行くわー。
これは日本人にとっては、結構行く可能性が低いときの返答ではないでしょうか。
でもフィンランドの人たちは、言葉 そのまま の意味だと受け取ります。
ですので、後に「行くか決めた?」と聞いてくることもしばしば。
ですから、心のままに、素直に言っていいんです。
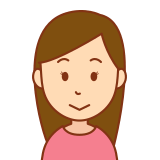
「あ、今日はケーキざんまいする予定だから無理!また今度ね!」
と言えば、

Niin! おっけー
で済みます。
フィンランドの人に、裏の意図、裏の顔、というものは存在しないのではないでしょうか。
とにかく透明。
それがフィンランド人。
楽しくなかったんですね(笑)わかりやすすぎて笑いました。
![]()
類似記事




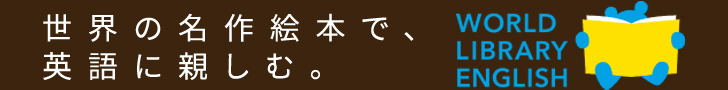


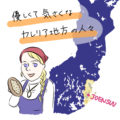
コメント